看護計画名:栄養状態の悪化に伴う改善・維持支援
栄養状態の改善・維持は患者の全身状態の安定や免疫機能の向上に不可欠です。看護師は患者の栄養摂取状況を継続的に評価し、適切な食事指導や栄養補助を通じてバランスの良い栄養状態の保持を支援します。本記事では栄養管理に関する看護計画と具体的な介入方法について詳しく解説します。
短期目標
・食事摂取量や内容に意識を向けて、自身の状態を理解できる
・必要に応じて補助栄養や経口補水を取り入れることができる
・食事環境を整えることで、安心して食事をとることができる
・家族と連携し、適切な食事形態を選択・継続することができる
長期目標
・自身の栄養状態を維持しながら日常生活を送ることができる
・体重・体力の維持または改善が図れる食生活を継続できる
・栄養補助や食形態の工夫を日常生活に取り入れることができる
・体調変化に応じて適切な栄養管理の調整ができる
O-P
・食事摂取量、食欲、食事時間、嗜好の変化
・体重変化、BMI、皮膚の乾燥や褥瘡などの身体所見
・血清アルブミン、プレアルブミン、CRPなどの栄養関連データ
・筋力・握力・ADLの変化
・口腔状態(義歯、口内炎、乾燥の有無)
・食事環境(姿勢、気温、周囲の騒音など)
・介護者の調理・食事介助状況
T-P
・栄養状態の定期評価と医師・栄養士との連携
・適切な食事形態への調整(刻み、ソフト食、ゼリー食など)
・経口摂取が困難な場合の補助食品や栄養補助飲料の導入
・食事時間や雰囲気の工夫による食欲刺激
・食事中の座位保持や嚥下を助ける環境調整
・口腔内の清潔保持・保湿ケアの実施
・食事摂取状況の記録と家族との共有
E-P
・栄養バランスのとれた食事の基本と重要性を説明
・体重や食欲の変化の記録と受診のタイミングを指導
・補助食品や市販栄養飲料の使い方を家族と共有
・水分摂取の意識づけと、適切な方法(少量頻回など)の助言
・食事介助時のポイントと声かけ方法を指導
・加齢や疾患に伴う栄養リスクについて具体的に説明
・定期的な栄養評価と支援体制の利用(訪問栄養指導など)を提案
O-P(観察・評価項目)の背景と根拠
栄養状態は治療経過や免疫力、創傷治癒、活動量などに深く関わる重要な健康指標である。
体重やBMIの変動、皮膚の状態、食事摂取量、血清アルブミン値などを継続的に観察することで、低栄養の兆候を早期に発見できる。
また、食欲の有無や嗜好、食事に対する意欲や摂食動作の評価は、介入の方向性を決定するうえで不可欠である。
T-P(ケア・処置などの実施項目)の背景と根拠
食欲が低下している患者には、食事の工夫(盛り付け、温度、香りの調整)や間食の活用が有効である。
嚥下障害がある場合には、食形態の調整やポジショニングの工夫が必要で、誤嚥の予防にもつながる。
栄養補助食品の導入や、必要に応じて栄養士との連携による個別メニューの提案も、継続的な摂取の支援として重要である。
E-P(教育・指導・生活支援)の背景と根拠
患者自身が栄養の重要性を理解し、食生活の改善意識を持つことは、自己管理力の向上につながる。
家族と共に、調理方法や食材の選び方を学ぶ機会を設けることで、在宅での栄養管理の継続を支援できる。
また、食事にまつわる楽しみを取り戻すような関わりは、心理面にも良い影響を与え、回復意欲にもつながる。
関連記事としておすすめ
似た症状やリスクが考えられる方は、以下の看護計画も参考にしてください
⭐︎誤嚥性肺炎の看護計画
⭐︎誤嚥性肺炎(在宅患者)に対する看護計画
⭐︎誤嚥・窒息予防の看護計画
⭐︎感染予防・感染コントロールの看護計画
栄養状態の改善・維持についての医学的知識や看護の要点は、看護roo!およびMSDマニュアル家庭版にて確認できます。疾患の理解と早期対応の重要性をふまえ、看護実践に役立つ情報源として活用できます。

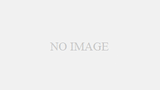
コメント